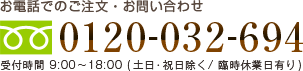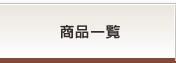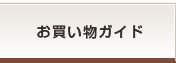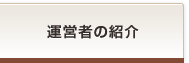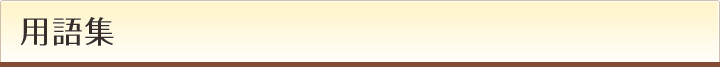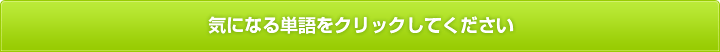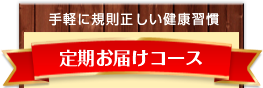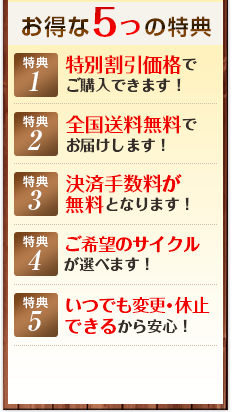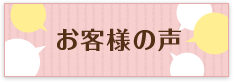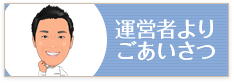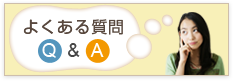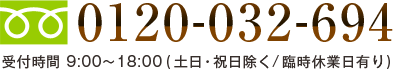- ガランタミン
-
Galantamineはアリセプトと同じアセチルコリン分解酵素阻害剤で商品名はレミニール(Razadyne, Reminyl, Nivalin)などです。軽度から中程度のアルツハイマー病に有効とされています。日本では臨床試験中で承認されていません
- 介護
-
心身の障害のある人へのに日常的で直接的な支援。介護保険法では、「要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について継続して常時介護を要すると見込まれる状態」としています。
- 介護予防事業
-
65歳以上の高齢者の方を対象に介護が必要となる状態を予防することを目的とした事業で、介護予防の講演会、専門職による訪問指導・相談などです。
介護予防事業は、65歳以上の高齢者全員を対象とする事業(一般高齢者向け事業)と65歳以上で介護保険を利用するほどではないものの介護が必要となる可能性の高い高齢者を対象とする事業(特定高齢者向け事業)があります。後者は、介護保険の認定で「非該当」になった人のうち「介護予防が必要」と判断された高齢者、または健診の結果「介護予防が必要」と判断された高齢者です。
一般高齢者向け事業としては、介護予防の講座や講演会などがあり、特定高齢者向け事業としては「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などを図るための教室、閉じこもり予防通所事業、保健師、栄養士、歯科衛生士等による訪問指導や個別相談などがあります。
また介護保険の認定で「要支援1」または「要支援2」と判定された高齢者を対象に予防給付としてデイサービスなどの通所サービスに運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケアなどの新しい項目が加わります。この予防給付のケアプランの作成は地域包括支援センターのケアマネージャーが行います。
しかしこの事業は要介護の高齢者を少なくしたり、その状態を遅くすることを目的としていますが、事業の実施、効果の判定など制度はあってもその有効性は未だ不明です。
- 介護保険
-
心身の障害があり介護を要する基本的には65才以上の高齢者を対象として介護サービスを提供する公的保険制度。
公的介護保険はオランダ、ドイツにあり、民間の介護保険は日本にもアメリカにもありますがここでは2000年にわが国で始められた介護保険について述べます。
介護保険法での介護サービスを受ける対象者は65才以上の高齢者および初老期認知症など15の特定疾患による障害のある40才以上64才までの人です。サービス受けるまでの手続きは、本人または家族らが市区町村へ介護認定の申請、訪問調査および医師の意見書作成、介護認定委員会による要介護認定および要介護度の決定、認定された要介護度に応じた介護サービス計画の作成、サービスの利用となっています。これには要介護認定への不服申し立て認定制度、サービス計画への家族等の意見の反映が盛り込まれています。
利用できるサービスは、在宅サービスとして、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期介護入所生活介護、福祉用具の貸与、認知症対応型共同生活介護などであり、施設介護を受ける場として介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。利用者は介護に要する全費用の1割を負担します。
介護保険制度での金の流れは、65才以上の高齢者および40才から64才までの国民からの保険料と国・都道府県・市区町村の公費を併せた資金が決められた護報酬に従って請求するサービス提供者に支給されます。提供者は利用者からの自己負担も受け取ります。
以下認知症の人と家族にとっての介護保険について述べます。
申請
通常、本人または家族が行いますが、居宅介護支援業者、介護保険施設長も行えます。認知症の場合、本人が申請をすることは極めて稀でしょう。初期で家族が気づかなかったり、あるいは気づいていても家族内で意見が分かれたり、恥ずかしいと周囲に隠したりして要介護認定の申請する時期が遅れることが考えられます。このため、介護サービスが早期に適切な時期受けることができるように、在宅介護支援センターなどに家族が気軽に相談でき、適宜に申請ができるようにする必要があります。また1人暮らしの認知症高齢者が居ます。成年後見制度や地域福祉権利擁護事業にも関係しますが、このような高齢者も申請できるようにしなければなりません。またまた介護保険が若年期認知症の人ー一部ですがーも介護サービスを受けられることを十分周知しておかなければなりません。
調査・認定
認知症は、原因の病気により、進行度により、人により、日により、さらには一日の時間帯により症状や状態が変化するものです。1回の短時間の訪問面接調査では把握できない状態や介護の困難さがあります。認知症は、軽度でもそれなりに介護は困難であり、中程度でもそれなりの困難さがあり、重度でも別な困難さがあります。認知症そのもの、あるいは認知障害の重症度と介護の困難度とは並行関係にはありません。認知症の重症度によってそれぞれ異なった介護上の困難さがあります。従って、目の前にいる認知症の人の状態だけでなく、一緒に生活しながら常時介護を続けている家族から認知症の人の状態を詳しく聞き出しす配慮が欠かせません。また認定に必要な「かかりつけ医の意見書」を書く医師も認知症と介護の困難さについての理解が望まれます。認知症の人の介護の必要性についての認定については介護保険が始まって以来すこしづつ改善されてきました。
サービス計画
介護支援専門員(ケアーマネージャー)による介護サービス計画の作成にあっては、個々の認知症の人の状態にふさわしい計画を立てなければなりません。ここに計画作成する人が認知症について正しく理解しておく必要があります。認知症の人は、認知症に加え、その人の生活歴、生活環境、性格が症状や状態に影響します。従って計画は個別的なものでなければなりません。
サービスの提供
認知症の人への介護サービスのメニュ-は多様になりましたが、サービスの量、質共に未だ十分とは言えません。特に認知症の人を対象としたグループホームは増加してはいますがまだ十分ではなく、利用料が高くて実際に利用できない人も少なくありません。デイサービスは量的に多くなりましたが、認知症の人の特性に配慮したセンターは少ないのが現状です。また特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設介護は大規模で画一的な介護になることが多く、それを改めるものとしてユニットケアが導入されつつありますが、その数はまだ少ない。さらにグループホームでもユニットケアでも認知症の人への専門的な介護が行われているはずですが、その質について課題が残されています。身体拘束のない、虐待のない介護が行われているとは言いがたい施設もあります。
介護サービスで忘れてはならないことは、若年期認知症の人が要介護認定を受けても実際にサービスが利用しにくい状況にあることです。高齢者の多いデイサービスや介護施設では若年期認知症の人に相応しいサービスが提供しにくい現実があります。今後の取り組みが待たれます。
- 介護家族
-
在宅で介護をしている家族のこと。他方、専門職として介護している介護専門職がいます。
在宅介護では家族内の特定の人が介護しているか、せざると得ないか、強制されていることが多く、狭義にはこの人のことを介護家族という。家族内で役割をもち協力し会っている場合は家族全体を介護家族とよぶこともある。
我が国の認知症の人-おおよそ3分の2-は在宅で介護家族に介護を受けて生活しています(健康保険組合連合会「痴呆性(ぼけ)老人を抱える家族全国実態調査報告」2000による)。これは日本だけでなく欧米でも多くの認知症の人は家族の介護を受けながら在宅で生活しています。いわゆる途上国では認知症の人のほとんどは家族の介護を受けています。すなわち認知症の人の介護の多くは介護家族で行われているのです。このことは認知症の人がどのような生活を送れるかは介護家族なしには語れないし、認知症の人への支援は介護家族への支援でもあります。
認知症の人はいろいろは家族のなかで介護を受けて在宅で生活していることは、認知症の人が介護家族からの影響を強く受けることであり、認知症の人を理解するには介護家族を理解しなければならりません。このため介護家族への支援に介護する家族の心と行動の理解は欠かせません。
以下のそのいくつかを列記、説明しますが介護家族の全てがこうした状態にあるわけではなく、介護家族の心身の状態、性格、人間観、認知症の人との人間関係、社会的な援助の状況によりさまざまであり流動的でもあります。
介護家族の心の動き
1)判断の遅れ
家族が認知症に気づくのに遅れることがあります.この遅れの背景には,認知症について間違った知識をもって病気によるもの忘れを老化現象と思い込んでいる場合があり、「親が認知症になってもらっては困る」という拒否したい心が働きがある場合があり、また「あのしっかりした親が認知症るはずはない」という否認する心が働いていることもあります。認知症に気づくのに遅れることで、治る認知症の治療が遅れたり,、認知症には不適切な介護を続けてしまい悪化させたりすることがあります。また早い時期にアルツハイマー病や脳血管性認知症に気づくことで生活や介護の予定が立てられるかかもしれないし、早期治療で進行を遅くしたり(アルツハイマー病の場合)、止めたりするここと(脳血管性認知症の場合)も不可能でなありません。
2)落胆
アルツハイマー病と診断されると,介護家族は落胆し悲しみ情けなく思います.と同時にこれからどのような生活が始まるのか,どのように介護したらよいのか不安にもなります.うつ状態になるかもしれません。この落胆は認知症の変化に従い、また懸命に介護していていもかかわらず認知症が悪くなったりする場合にも抱く気持ちでしょう。
3)期待
介護家族のなかには,アルツハイマー病と診断されたにもかかわらず,診断が間違ってはいないか,治るのではないかと治癒への期待を抱く人がい少なくありません。これは家族の心とて自然であり当然です。この期待をもって治る治療、良くなる治療を求めて病院や医師を転々とすることになります.さらにはいろいろな民間療法を試みたりもします.このことは結果的よりよ医療や介護を受ける機会を得ることがあるかもしれませんが、むしろ期待を裏切られてしまうことの方が多いと思われます。むしろ期待と受容がバランスのとれていることが望ましいと思います。
4)悲嘆
落胆と似ている心の状態ですが介護家族は認知症の親や配偶者の姿を毎日見ることは辛いことです.尊敬していた親や配偶者の発病した認知症になった姿を見ることの悲しみは深く,癒し難いものでしょう.このため家族が介護の意欲をなくしたり、施設へ入居させることを考えたり、無理心中を思ったりすることになります。この悲嘆の気持ちを癒す方法の一つが同じような経験をしている介護家族同士が話し合い、思いを共有することでしょう。家族の集いの役割の一つです。
5)不安
認知症の人の在宅介護が長くなると将来へのいろいろな不安が介護家族を心をよぎります。家族の生活を犠牲にして認知症の人を中心にした生活がいつまで続くのだろうか、もっと認知症がひどくなったら家で看れるのだろうか、また家族が病気になって介護できなくなった時にどうなるのだろういかといった不安です。介護家族は、医師らから具体的に認知症に将来予測されることの説明を受け、地域で利用できるデイサービスやショートステイなどの社会資源を利用することを介護計画のなかに入れて少しでも将来への不安を和らげたいものです。
6)怒り
介護家族は、「認知症てしまってどうしてこんなに私を困らせるのだろう」と認知症の人が病気であることを忘れ,被害者意識が強くなり怒りや被害者意識の気持ちが生じることがあります.この気持ちが高じて認知症の人への暴力,さらには殺人や心中にいたる状況に追いやられることもあります.特に介護家族が孤立していたり、密室の介護のなかで起こりやすい気持ちでしょう。気軽に相談できる人や電話相談を早め利用しましょう。
7)孤立感
介護家族のなかには,自分の生活を犠牲にしてまで苦労が多い介護しているのは自分一人だろう,誰も理解してくれないし助けてもくれないと孤立感を抱くことがあります.この孤立感は被害意識を強め、認知症の人への不適な介護、虐待へつながりかねません。家族や周囲の人たちに介護の苦労を理解してもらい、家族の集いなどに出席してみるともっと困難な介護を続けている家族を知るかもしれません。
8)自責
認知症が悪くなったのは自分の介護の方法がよくないからだと自分を責める介護家族がいます.直接介護してない認知症に理解のない周囲の人からそのような指摘をされて、一層自責の念にかられることがあります。
不適切な介護で認知症の人の状態を悪くすることもありますが、適切に介護してもアルツハイマー病など病気そのものが進んで悪くなることもあります。周囲の人に認知症を理解してもらい、デイサービスやショートステイも利用して少しでも余裕のある介護をすることで自らを責めることは避けたいものです。
9)後悔
自責の念とも関係しますが特別養護老人ホームや老人保健施設あるいは精神病院に認知症の人を入所・入院させたことに対して、何か自分が楽にになるため認知症の人を犠牲にしたのではないかと後悔する介護家族がいます。条件が整のわない場合には認知症の人にとって在宅介護より介護施設や病院で生活した方がよい場合があります。後悔の気持ちで悩むより頻回に面会にゆき認知症の人の生活を見て納得するかもしれませんし、そうでなければ別な方法を考えたい。
後悔の思いは、介護が終わった家族が抱くことが少なくありません。「あの時もったやさしく声をかけてみてあげればよかったのに」「経管栄養をしてまで長生きさせたのは本人によかったのだろうか」など思い出とともに後悔の気持ちがわくことは珍しくありません。家族の集いや電話相談などで介護を経験した者どうしが語り合ってその思いが和らぐでしょう。
10)喜び
介護家族のなかには、医師からは良くならない治らないと言われたが、介護の工夫をして認知症の人と話が通じるようになった,表情が穏やかになったと介護のやりがい,自分の努力が報われたという喜びを抱く場合があります。介護家族は介護から失うものばかりではなく得るものもあるのです。共に喜びたいものです。
11)神経症・心身症
介護の疲労、不安、孤立感などが続くと介護家族は、うつ状態の神経症になったり、「自律神経失調症」、頭痛、肩こり、胃潰瘍、過敏性腸症といった心身症になったり、不眠になったりすることが少なくありません。デイサービスセンターやショートステイを利用したりして心身の休養をとり、買い物をしたり、小旅行をしたり、理解ある友人知人と語り合うのもよいでしょう。症状が重いと通院したり入院しなければならないこともあります。
- 介護手当
-
認知症高齢者の在宅介護には経済的な負担は軽くはありません。これを補うものとして、介護手当があります。国の制度として「特別障害者手当」があり、認知症の人も対象となっていますが、常時介護が要する心身が重度の状態であることが条件で、認知症の場合ではアルツハイマー病末期や重度の脳血管障害で常時臥床といった状態が該当します。なお手当は、年齢に関係なく月額6万円ほどが支給されます。介護保険前にあった市区町村の介護手当は制度導入後はほとんど行われていません
- 介護支援専門員
-
介護保険制度とともに導入されたわが国独自の国家資格専門職。通称、ケアマネージャーと呼ばれています。介護保険サービスのケアプランの作成、サービスの調整、要介護者の調査などを行います。専門員一人が担当する事例が多くニードにあったプランが立てられない、施設や団体と独立していない、報酬が十分でないなどの問題はありますが、介護保険制度の要となる重要な職種です。日本介護支援専門員協会があります。
- 介護者
-
介護者とは、心身の障害者への介護を行う人のことで、在宅で介護する家族(介護家族)と介護を仕事とする介護専門職に分けることができます。。後者は、介護保険施設、デイサービスセンターで勤務する人やホームヘルパーがいます。介護専門職には介護福祉士およびホームヘルパー養成講座受講者の有資格者がほとんどです。
- 加齢関連認知低下
-
主に加齢に伴う認知機能の低下で、軽度認知障害でも認知症でもない状態。英語でAging-associated Cognitive Decline(略称:AACD)といい、国際老年医学会では以下の診断基準を示しています
1.本人または信頼できる他者から認知的低下が報告されること
2.始まりが緩徐で6 ヶ月以上継続していること
3.認知的障害が、以下のいずれかの領域での問題によって特徴づけられること。
(a)記憶・学習、(b)注意・集中、(c)思考、(d)言語、(e)視空間認知
4.比較的健康な個人に対して適応可能な年齢と教育規準が作られている認知評価おいて異常があること。
5.除外規準
上にあげた異常のいずれもがMCI または認知症の診断に十分なほどの程度でないこと。
身体的検査や神経学的検査や臨床検査から、脳の機能低下を引き起こすとされる脳の
疾患、損傷、機能不全、または全身的な身体疾患を示す客観的な証拠がないこと。
- 回想法
-
認知症の人は、新しい記憶は失われても古い記憶はかなり保持されており、遡って数十年の記憶が失われて過去に生きている状態になることも少なくありません。こうした認知症の人へ昔の記憶や生きている世界のなかで語り合い残存した機能を十分に発揮することで精神的安定をもたらし知的機能の改善を図ろうとする治療方法が回想法です。実際には、集団または個別に認知症高齢者の若い頃の写真、新聞、身の回りの物などを見たり読んだりしながら、それについて話し合ったり、思い出を語ります。このためには個々の認知症高齢者の生活歴を知り、それに合った資料や材料をを用意しなければなりません。一概に昔の記憶といっても楽しい記憶もあれば悲しい記憶もあり、思い出したくない記憶もあり、このうちできるだけ思い出しても精神的混乱を招かないような記憶にとどめた回想法を行う配慮が必要です。参考図書としては、野村豊子ら著「回想法への招待」(筒井書房発売)があり、愛知県師勝町には回想法センターがあり研修を受けることができます。
- 学習療法
-
読み・書き・計算を中心とする教材を用い、学習者(認知症の人)とスタッフ(学習療法スタッフ)がコミュニケーションを取りながら行う学習によって大脳の前頭前野を活性化し認知症の人の認知機能やコミュニケーションを改善させるとされる療法で川島隆太医師らが開発したものです。認知機能を短期的に改善する効果はあると思われるが、認知症の予防効果については不明です。
- 家族
-
家族とは夫婦を中心とした血縁関係にある心情的経済的法的に結ばれた生活共同体と定義することができるが、これは「古典的な家族定義」であり、現代社会では、その形態や役割は変化しています。
我が国では家族の形としてみると、家族構成員が少なる傾向が顕著です。高齢夫婦二人暮らし、高齢者の一人暮らしが多くなっています。またこれに関連して家族の役割として、高齢者の介護機能が低下しています。これは特定の地域への人口の集中など社会経済状況と共に、儒教思想や家意識の希薄化など日本人の考え方の変化によると思われます。
こうした変化しつつある家族のなかに知症の人も介護する家族も置かれています。3世代家族でも昼間一人に置かれたり、老老介護と言われるように認知症の高齢者を高齢者が在宅で看ている場合も増えています。さらに一人暮らしの認知症の人も少なくありません。
家族の形態と役割の変化、すなわち高齢化、構成員の少人数化、介護機能の低下という家族の変化は今後も続くことは確実であり、こうしたなかで認知症の人の介護は基本的には家族が診る事のではあるが社会的な補完は不可欠です。これなくして認知症の人もその家族も人間的な生活を送るとはできません。そのひとつが介護保険制度です。社会的な役割がいくら重視され整っても家族でなければできない役割が残ります。それはは家族の心情的な絆とそれに基づく認知症の人への精神的な支えと考えます。とはいえ認知症の人への家族の関わりは、理性的、情緒的、倫理的、法的、経済的、文化的、宗教的な関係のなかで個々の家族が決めることであり、認知症の人とその家族の思いや願いを支援することも社会的支援として大切です。
なお認知症の人について語るとき認知症の人も家族の一員であることを銘記しておきたい。
- 家族会
-
認知症にかかわる当事者団体としての家族会は、全国団体としては社団法人呆け老人をかかえる家族の会がありますが、地域、施設単位の家族会も数多くあります。その実態はよくわかっていませんが、呆け老人をかかえる家族の会が1995年に行った全国調査では、その数は466団体でした。実数は1000を越えると同調査報告では推計しています。運営主体は、病院、老人保健施設、老人福祉施設など施設、市町村、社会福祉協議会、保健所などで、主な活動は家族の集いでその他に、会報の発行、各種行事などでした。運営に当事者が中心となっている家族会は少なかった。
家族会の中心となる家族の集いは、介護経験した家族ではわからない介護の辛さや悩みを語り合い共感し、互いに慰め励ますことに意義があり、さらに介護の工夫や会議に関わるさまさま情報を共有することも家族会の目的です。全国団体の呆け老人をかかえる家族の会は、さらに啓発、要望、活動交流、国際交流まで活動の幅を広げていると言えます。
しかし大小の差はあれ、多くの家族会は会員が少ない、会員が固定化し活動が停滞する、活動資金が乏しいなどの問題を抱えていますが、認知症に関わる当事者団体としての役割を発揮しながら活動を続けているところも少なくありません。
なお欧米では家族会という名称の団体は少なく、Self-Support Group(自助団体)と呼ぶことが多い。
- 家族性プリオン病
-
致死性家族性不眠症(Fatal Familial Insomnia:FFI)のことで、幻覚、不眠症、不随意運動、認知症を呈する神経変性疾患。プリオン蛋白遺伝子の変異した家系に見られるが、日本では極めて稀です。
- 柄澤式老人知能スケール
-
正式には「柄澤式老人知能の臨床的判断基準」とよび、1981年に柄澤昭秀氏が開発したものです。認知症の人の日常生活能力と日常会話・意思疎通のついて6段階に分類し知能状態を判定するものです。基準には認知症の判定を目的にしているとは明記されてはいませんが、認知症の人の重症度を判定するに優れ、わが国で広く使われていましたが、特に厚生省の「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」が提案されて以降、使われることが少なくなったようです。
- 画像診断
-
映像など見える形で診断すること。以前はレントゲンによる胸部の単純撮影、造影剤による脳血管撮影などにレントゲン撮影に限られていましたが、近年の医療技術の進歩により超音波断層撮影法、コンピューター断層撮影法(CT)、磁気共鳴断層撮影法(MRI)などが病気の診断には欠かせない画像診断になっています。認知症の分野では、アルツハイマー病や脳血管障害ではCTやMRIは不可欠な画像診断です。しかもCTでは認知症の人に負担をかけない簡単で重要な診断が行え、MRIではアルツハイマー病の早期の脳の変化や脳血管性認知症の細かい脳梗塞を確認できます。この他、PET(Positoron Emission Tomography:陽電子放射型断層撮影)では脳の血流量、脳酸素消費量、脳糖消費量などを測定でき、SPECT(Single Photon Emission Couputed Tomography:単光子CT撮影法)では脳の血流量が測定できます。これらの画像診断はCTやMRIと比べ脳の局所の働きをみることができる利点があり、アルツハイマー病などの診断の補助して有用ですが、特定の医療機関でないと受けらることができない検査です。
- 関節拘縮
-
長期臥床に伴う四肢、特に下肢の運動が極端に減少し股関節、膝関節、足関節の拘縮が生じやすい。一端拘縮が起こると他動的に動かそうとしても運動制限があり疼痛を伴いますます運動が制限され一層拘縮が進むという悪循環になりやすい。拘縮は四肢の変形だけでなく褥創の発生要因にもなります。予防が大切で、通常重度の認知症でも長期に臥床する必要性は少なく、車椅子に座り、車椅子で移動し、食事は食堂でとり、排泄もベット外で行う、入浴するなどできるだけ通常の日常生活を送るようにすることでほとんどの拘縮は防げます。やむなく臥床が長くなる場合は、特に下肢を他動的に動かすることが予防になります。